いよいよ明日が参議院選挙の投票日。
自公が過半数を切り、自公政権の下野へと前進する時。
立憲民主党、日本共産党、れいわ新選組、社民党が議席を増やしてほしいと思う。
裏金・脱税問題、世界平和統一家庭連合との癒着を断ち切り、政治が透明・オープンになることに期待する。森友問題などの政治の闇が明らかにされるべきだ。
選挙期間中、メディアからファクトチェックがされたことはいいことだと思う。
例えば、朝日新聞
(ファクトチェック)
外国人への生活保護、日本人より優遇されている?
2025年7月17日 5時00分
■インターネット上の言説「外国人への生活保護が優遇されている」(6月23日、X〈旧ツイッター〉に投稿されて拡散した動画)
【誤り】厚生労働省保護課によると、生活保護の受給に関して外国人が日本人より有利になることはない。日本に住む外国籍の人が受給するには、日本人と同様に、その資産や困窮度が調査される。在留資格によって受給資格がない外国人もいる。
■優遇なく、身元保証人も調査対象
動画は、あるタレントの画像をつなぎ合わせたもので、このタレントが「激怒」とうたい、その理由として「外国人への生活保護が優遇されている」と主張した。Xの匿名アカウントに投稿された6月23日以降、今月15日までに285万回以上、表示された。
外国人の生活保護をめぐっては、参政党が「外国人への生活保護支給を停止」と政策に掲げている。
生活保護行政を担う厚生労働省保護課は朝日新聞に対し、生活保護の受給に関して外国人が日本人より有利になる要件があるかについて、「ない」と回答した。制度上の優遇はない、ということだ。
そもそも外国人は、生活保護の対象なのか。
生活保護法は、生活に困窮するすべての国民(日本人)に受給資格があると定める。一方、1954年の旧厚生省の局長通知で、日本に住む「生活に困窮する外国人」に対して、保護を準用できるとしている。
日本は戦前に台湾や朝鮮半島を植民地にし、両地域の人々は52年のサンフランシスコ講和条約発効まで日本国籍を持っていた。通知は歴史的経緯を踏まえつつ、こうした人々については特に、「条約発効後も日本に在留する者多く、生活困窮者の人口に対する割合も著しく高い」などと、保護の必要性に言及していた。
外国籍の場合、対象は、日本人との公平性を考慮し、日本で自由に働くことができる永住者や日本人の配偶者、日系3世ら定住者、在日コリアンなどの特別永住者、難民の認定を受けた人らに限られる。留学や技能実習、特定技能といった就労に制限のあるビザで滞在する人は対象外だ。
生活保護は世帯単位で受ける。厚労省によると、受給対象になるか否かの審査は、世帯主の国籍を問わず、同じ基準で実施される。働けるかや、資産があるかなどについて調査を受ける。資産があれば現金化して生活費に充てなければならない。
外国籍の場合はさらに、受給目的での入国を防ぐという観点から、困窮に至った経緯だけでなく、ビザ取得時に示した身元保証人の情報なども調査の対象になる。
■受給世帯、外国籍の3・36%
では、どのぐらいの数の世帯が実際に受給しているのか。
2020年の国勢調査の結果を使い、世帯主の国籍別に受給世帯の比率を算出したところ、日本籍は計5435万世帯のうち157万世帯(2・89%)が、外国籍は136万世帯のうち4万6千世帯(3・36%)が受給していた。
世帯主の主な国籍別の受給世帯数と受給比率は、韓国・朝鮮の2万9千世帯(14・43%)、中国の5700世帯(1・62%)、フィリピンの5100世帯(5・41%)だった。
高齢世帯が占める割合は全体で56%だが、韓国・朝鮮籍は68%。母子世帯が占める割合は、全体が4・43%だったのに対し、フィリピン籍は48・41%だった。
生活保護行政に詳しい花園大学の吉永純教授は、「在日韓国・朝鮮籍の高齢世帯の受給比率が高いのは、日本では長い間、外国籍の人が制度的に国民年金に加入することができず、低年金者が多くなっているためだ。また、フィリピンは日本人配偶者と離婚し、子どもを抱えて困窮した女性が多いことが影響している。いずれも歴史的な理由があり、生活保護の利用継続を認めることは、理にかなっている」と話す。(石田耕一郎)
(ファクトチェック)日本人が奨学金を借りて大学に通う中、中国人は無料?:朝日新聞
「農林水産予算を10倍?」野田氏を批判した小泉氏のXは「誤り」:朝日新聞
選挙は、生活防衛が最大の焦点だ。
消費税減税で、日本に暮らすみなが元気になることだ。
働くもの、虐げられたもの、生活者の暮らしと人権が守られること。
人間にファーストもセカンドもない。
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ChatGPTと対話した。
差別とは排外主義について。
歴史を直視する勇気が必要。
それをもとに 整理した。以下の通り。
……………………………………………………………………………………………………
共に生きる社会のために
― 植民地支配の歴史を直視する
1. 歴史の出発点 ― 日本の植民地支配とその影響
日本における移民問題を考える際、まず重要なのは、かつて日本が行った植民地支配の歴史に向き合うことである。1910年の日韓併合以降、日本は朝鮮や台湾を統治し、多くの人々を「日本臣民」として組み込んだ。その結果、戦前には数多くの朝鮮・台湾出身者が本土に移住し、日本社会の一部として生活していた。
しかし、1945年の敗戦とポツダム宣言受諾によって、日本はこれらの植民地を放棄した。1952年のサンフランシスコ講和条約発効とともに、旧植民地出身者は本人の意思と無関係に日本国籍を失い、いわば「望まぬ外国人」とされる立場に追いやられたのである。これが、今日まで続く在日コリアンをはじめとする特別永住者の存在の起点である。
2. 敗戦後の制度と差別 ― 残された課題
戦後、在日コリアンらには1965年の日韓請求権協定により永住資格が与えられ、1991年には特別永住制度が創設された。しかし、参政権や公務就任権は依然として与えられておらず、社会的には「いつまでも外から来た者」として扱われがちである。これは「日本社会に根づいた人々」としての認識が欠如している証でもある。
また、朝鮮学校に対する支援の不足や、メディアや教科書での歴史的扱いの偏りも、偏見や差別を温存する一因となっている。特に北朝鮮による拉致問題報道の影響で、在日韓国・朝鮮人に対するヘイトスピーチが顕著に増加した。これは、個人の人権と集団の出自が混同され、無関係の市民が憎悪の対象とされる危険な状況である。
3. 管理から共生へ ― 日本の移民政策の転換点が必要だ
日本の移民政策はこれまで一貫して「管理主義的」であった。政府は移民を「人手不足対策」として扱い、技能実習制度や特定技能制度を通じて限定的な労働力を受け入れてきた。しかしこれらの制度は、家族の帯同や定住を想定しておらず、移民を「一時的な存在」として位置づけている。
MIPEX(移民統合政策指数)において、日本は統合政策の欠如から低評価を受けている。特に政治参加、教育、反差別の分野で大きな遅れをとっており、共生社会を実現するには構造的な見直しが必要である。
※ Migrant Integration Policy Index | MIPEX 2020
4. 共生社会の実現に向けて ― 教育と社会の役割
共に生きる社会の実現には、制度改革だけでなく社会全体の意識の転換が必要である。第一に、地方参政権の付与や差別禁止法の制定など、法制度面での整備が求められる。また、日本語教育の充実や多文化理解教育の推進により、外国にルーツを持つ子どもたちが安心して学び、暮らせる環境をつくることが不可欠である。
さらに、草の根の取り組みも重要である。
メディアにおいても、旧植民地出身者の歴史や現在の暮らしを積極的に伝えることが、偏見を払拭する大きな力となる。
5. 歴史を学び、未来を選ぶ力をつくる
私たちは、過去の過ちに正面から向き合い、そこから学ぶ姿勢を持たねばならない。旧植民地出身者に対する差別の歴史を知ることは、単なる謝罪や反省にとどまらず、共に生きる未来をつくる出発点である。
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
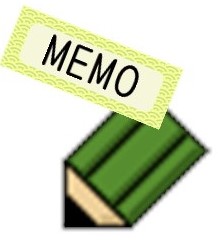


……………………………………………………………………………………………………




……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

